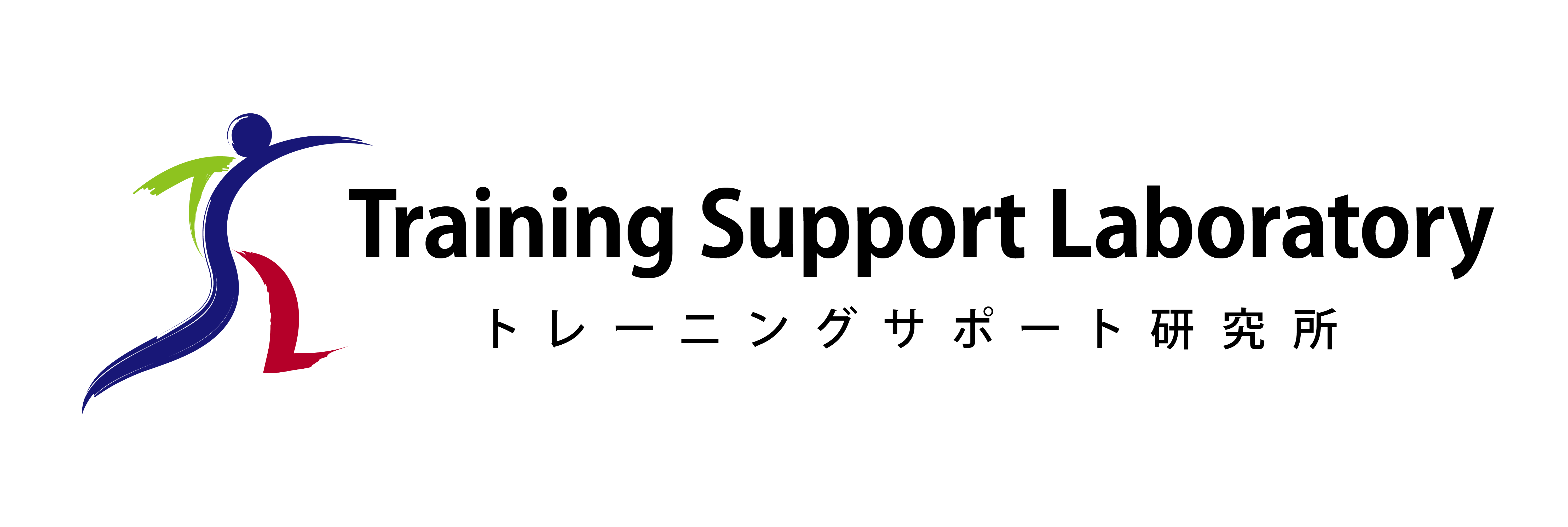イップスの原因
イップスの原因は、一連の動作を過剰に繰り返し行った結果による運動障害であることが改めて明らかになりました。
イップスの原因とは
イップスの原因と発生フロー
最近のアンケートデータです。
当研究所にお越しいただいたイップス症状を抱える選手へ、直接アンケートを取ってみたところ、改めてイップスの原因が、過度な同一動作によって起きていることが判明しました。以下その結果をもとに簡易的にイップスの発生フロー図(図①)を作成しました。
なお、過度な同一動作を行ってしまう“きっかけ”においてもアンケートをいただきましたので、そちらも付随して説明いたします。
以下図①の<きっかけ>と<原因>、及び※注釈①、②に関しては、当研究所独自の解釈及び表現を使っています。
図①
イップスの<きっかけ>
悩み始めたきっかけとは?
図①のフロー図をもとに、図②及び以下説明をお読みください。
まずは、そもそも自身の動作が気になるようになったきっかけは何ですか?といった質問をしました。対象は直近計39名(10代~40代男女)のイップスを抱えている選手。内訳は硬式野球21名(55.3%)、軟式野球16名(42.1%)、ソフトボール1名(2.66%)、テニス1名(2.6%)
※複数選択可(何がきっかけかをひとつに確定、判別することが困難なため)
※軟式野球とソフトボールの両方を選択している選手が1名
図②
以上図②のアンケート結果から、イップスのきっかけは多様に存在することが改めて判明しました。上位3つについて補足します。
1番多い声が「予期せぬ暴投」(48.7%)でした。予期せぬ暴投についてもう少し具体的な例でいうと「普通にブルペンで投げていて、たまたま捕手の頭上にある屋根に当ってしまった」、「内野ゴロを処理し一塁へ送球した際、一塁手へ暴投してしまった」「オフ明けの久しぶりのキャッチボールで、暴投してしまった」等です。どれもチョーキングの状態ではなかったものです。
2番目に多い声が「チョーキング(あがり、分析による麻痺)」(41%)がきっかけでした。指導者や先輩等の過度な叱責もこのなかに含まれます。
3番目に多い声が「フォームの修正」(25.6%)でした。youtube等の動画を見ては自身で修正を加えたものや、指導者の助言によるフォーム修正(強制指導及び合意済み両方含む)等です。
本当に皆さん様々な”きっかけ”があったようです。
なお下に列記してあるコメントは、図②のアンケートで「その他」を選択した選手の回答です。
・ブランク明けの試合での違和感
・バッティングピッチャー
・頭部へのデッドボール
・先輩に指摘されたこと
・大会前の練習試合中、登板している最中に突如投げ方がわからなくなった
イップスの<きっかけ>※2種類に分けてみました
「アクシデント型」と「チョーキング型」
図②のアンケート結果をもとに、イップスの<きっかけ>を当研究所独自に判別してみました。以下「アクシデント型」と「チョーキング型」の2種類に分けました(わからない、その他は省略)
■「アクシデント型」
・『フォームの変更』:球速やコントロール向上を目指すためのフォーム修正等
・『肩肘の故障』、『肩肘以外の故障』:怪我(十分に癒えていない状態で練習や試合に参加)等
■「チョーキング型」
・『チョーキング』、『予期せぬ暴投』:過度に緊張している状態でプレーしミス。又はミス直後によるプレッシャーが続いている状態での過度な反復動作によるもの
イップスの<原因>
何が原因なのか?
イップスの原因は、過度な同一動作(同じ動きを何度も繰り返すこと)
図③

図③は、イップスのきっかけ後、本来の動作に戻るよう過度な反復練習行いましたか?(例:テイクバック、リリースポイント(インパクト)、手首、股関節、体重移動といった局所意識を伴っ反復練習等)の質問に対して「はい」と回答している選手が39名中28名(71.8%)、「いいえ」の回答が6名(15.4%)、「わからない」5名(12.8%)でした。以降自身の動作をコントロールができなくなっていったようです。7割以上の選手が過度な反復練習を行っていることが分かりました。
これらの結果からも、2008年『体育の科学』にてイップスの解説をされていた工藤和俊先生(東京大学)の解説は事実に即していることがわかります。※過度な反復動作例(練習例)は、当研究所のホームページ「注意!やってはいけない反復練習」にまとめています(イップス症状を抱えている選手がほぼ100%といっていいほど行っていた反復練習です)。参考にしてください。
一旦まとめます。すなわちイップスは同じような動きを過度にやり過ぎたことが原因ということです。さらに故障が癒えていない状態や、プレッシャーがかかり一時的に筋硬直が起きているチョーキング状態の時等に、同じ動作やり過ぎるとイップスを発症するリスクが高くなるということです。それまでと異なる関節軌道(神経回路)が出来上がってしまいます。これがイップスです。ということは、上述のような状態にある時に、過剰な同じ動作をしなければイップスにならないということが言えます。
なお、よく取り沙汰されているイップスの心理的な問題ですが、それは本質的な問題ではありません。一つのきっかけとその後の問題です。特にイップスにかかった後の問題です。”簡単に出来た動作が出来なくなっている”ことの焦りや苛立ち、そして不安です。特に本来のパフォーマンスとの動作(感覚)のギャップが殊の外影響しています。その状態を選手自身が「心理的、精神的な問題」等と誤認してしまったり、さらに周囲がそのような解釈をしてしまうことで、今度は更なる二次的な問題が起きてしまうので要注意です。
さらに、直接選手からヒアリングして改めて分かってきたこと
一部、または複数個所を必要以上に意識して(試行錯誤しながら)動作をしていた
局所意識と局所修正
過度な反復練習を行っている際、以下注釈①、②を行っていたことも、改めて当研究所の聞き取りで明らかになりました。今回のアンケート回答者で「はい」と回答した28名全員(100%)が行っていました。
※注釈①過度な局所意識
過度な局所意識とは、動作の一部分を必要以上に意識して行う運動のことです。例えば、テイクバックの軌道やTOPの位置を意識しながら投げる練習を行うことです。
※注釈② 過度な局所修正
上述※注釈①と連動。「ああでもない、こうでもない・・」と必要以上に関節の動きを修正しながら反復練習を行うことです。この過程は、ほぼ全員の選手が行っています。
局所意識、局所修正でここ数年よく耳にすることは、youtube等のワンポイント動画やメジャー等の超一流選手のフォーム及び練習方法をよく考えずにそのまま採用することです。自身のフォーム改善や日々の練習にそっくりそのまま当てはめ、必要以上に反復練習を行っていることです。結果、意に反する動作は勿論、継ぎ接ぎだらけのフォームが定着している選手も少なくありません。(自身のフォームと適合するかどうかをまずは慎重に考える必要があります)。つまり、良かれと思って取り組んだことが、かえって一連の動作に不適合を起こし、イップスの原因に繋がったりイップス症状を悪化させているように窺えます。
過度な反復練習の<結果>
<きっかけ>⇒<原因>⇒<結果>
こうして本来のフォームが崩れ、イップス(局所性ジストニア)が発生していることが改めてわかりました。もしイップスにかかると、何事もなかった以前のフォームを再現することが非常に困難になります。何故なら過度な反復練習(局所意識及び局所修正)により、それまでとは異なる神経回路が出来上がってしまうからです(意に沿わない動きが定着してしまうからです)。
以前のフォームが思い出せない、思い切り腕を振れない等の症状を選手が訴えるのは当然のことなのです。
メッセージ
当研究所のホームページを閲覧いただいている選手、指導者、関係者の方々へ
イップスは、一定のフォームを有している選手であれば、技能レベルや年齢に関係なくかかり得る運動障害だと考えられます。当然のことですが、当該競技に真剣に取り組んでいる選手や人一倍向上心が強い選手ほど、より精度の高い技能の獲得を目指しているため、必要以上に躍起になって過度な反復練習を試みる傾向にあります。責任感が強く問題意識の高い選手も同様。選手自身は勿論、指導者、ご父兄の方々はその点注意が必要です。